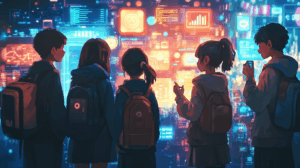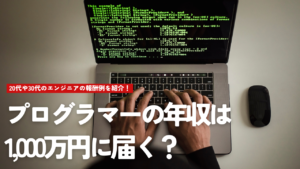- 「Webエンジニアはもう終わった」
- 「AIに仕事を奪われる」
- 「スクール卒ばかりで飽和してる」
そんな声を最近よく耳にしませんか?
しかし、果たして本当にWebエンジニアは“オワコン”なのでしょうか?
この記事では、SNSやYouTubeで拡散されるネガティブ情報の真偽を検証しながら、AI時代におけるWebエンジニアの立ち位置や、生き残るための戦略を徹底解説します。
現役エンジニアの視点と、AIを武器にできる次世代スキルセットのヒントもお届けします。
これからエンジニアを目指す方や、キャリアに迷っている方は必読です。
- Webエンジニアは本当に飽和しているのか?
- AIの進化とWebエンジニアの共存関係
- 年収・働き方のリアル
- AI時代におけるスクール選びのコツ
- “やめとけ”じゃなく“やり方次第”
AIプログラミングを学ぶならココ!
おすすめのスクールTOP3
| サービス名 | 1位 デジハク生成AI | 2位 SAMURAI ENGINEER | 3位 DMM 生成AI CAMP |
|---|---|---|---|
 |  |  | |
| おすすめ度 | |||
| おすすめ ポイント | 副業・収益化に特化した実践型スクール。案件獲得までサポート | 未経験から仕事で使えるスキルがしっかり身に付く | Pythonを活用した生成AIの開発に特化したプログラム |
| AIコース | MINIコース: 生成AIの基礎からクリエイティブ制作まで学べる。 148,000円~ PROコース: 業務効率化・AIアプリ開発・ビジネス実装まで網羅。教材無期限閲覧可能。 298,000円~ | AIアプリコース: Pythonを用いた AIアプリ開発を学べます。 693,000円~ 業務改善AI活用コース: ChatGPTやExcelを活用した 業務効率化について学べます。 213,950円~ オーダーメイドコース: 自由に組み合わせが可能 594,000円~ | プロンプト エンジニアリング: ChatGPTに的確な指示を 出すためのテクニックを 学べます。 198,000円 生成AIエンジニア: Pythonの基礎から応用までを 体系的に学べる。 296,000円 |
| 入学金 | なし | 99,000円 | ― |
| 給付金制度 | ― | あり (AIアプリコースが対象) | 対象 |
| 無料体験・相談 | 無料説明会あり (毎日10:00〜22:00) | 無料カウンセリングあり (40分~) | 無料相談あり |
| 公式サイトでチェック | 公式サイトでチェック | 公式サイトでチェック |
Webエンジニアはやめとけ?AI時代の現実と真実を暴く

- 「Webエンジニアはもうオワコン」
- 「AIに仕事を奪われるだけ」
- 「スクール出ても稼げない」
そんなネガティブな声がネットにあふれる今、「これからWebエンジニアを目指しても大丈夫なのか?」と不安を感じている人も多いはずです。
確かに、AIの急速な進化やエンジニア人口の増加により、“ただのコーダー”が淘汰される時代は始まっています。
しかし一方で、「AIを使いこなせるWebエンジニア」には新たなチャンスが広がっているのも事実です。
本章では、Web業界の現状や将来性、リアルな年収事情からAI時代に求められるスキル、さらに学習方法の選び方まで徹底解説。
- 「Webエンジニアやめとけ」と言われる理由を冷静に分析
- SNSやYouTubeでのネガティブ情報の背景とは
- プログラミングスクールの選び方が未来を分ける
- 【初心者向け】今から始めるならRanteq、サムライ、DMMの違いを知ろう
迷えるあなたが“進むべき道”を見つけられるよう、真実だけをお届けします。
「Webエンジニアやめとけ」と言われる理由を冷静に分析

近年、「Webエンジニアはやめとけ」という言葉を耳にする機会が増えています。その背景には、複数の現実的な課題と社会的な誤解が絡んでいます。単なる煽りや根拠のない否定ではなく、実際に存在するリスクや業界構造の変化を理解することで、このフレーズの本質が見えてきます。
まず大きな要因の一つが、エンジニアの供給過多です。プログラミングスクールや学習サービスの充実により、未経験からWebエンジニアを目指す人が爆発的に増えました。その結果、初級レベルの案件には多くの人が殺到し、単価が下がりがちに。スキルの差別化が難しいまま市場に出てしまうと、「思ったより稼げない」「仕事がない」と感じるケースが少なくありません。
また、AIの進化も無視できません。ChatGPTやCopilotなどの登場により、コーディング作業の一部は自動化が進んでいます。ただしこれは、単純なHTMLやCSSのマークアップのような反復作業に限られ、設計・実装・最適化などの高付加価値な仕事は引き続き人間の手によって行われています。言い換えれば、「AIで代替されるスキルだけを持っていると厳しい」というのが実情です。
さらに、会社によっては激務な環境も依然として存在します。ベンチャー企業や受託開発の現場では、短納期でのリリースや仕様変更への即時対応が求められ、ストレスが高くなりやすい傾向にあります。未経験者がこうした現場にいきなり飛び込んだ結果、現実とのギャップに失望して「やめとけ」となることもあります。
このように、「Webエンジニアやめとけ」という声の裏には、スキルのミスマッチ、過度な期待、そして急速な業界の変化という複数の要素が絡んでいます。ただし、それらを正しく理解し、乗り越える準備をすれば、むしろ今は「次の成長チャンスが広がっているタイミング」とも言えるでしょう。
SNSやYouTubeでのネガティブ情報の背景とは
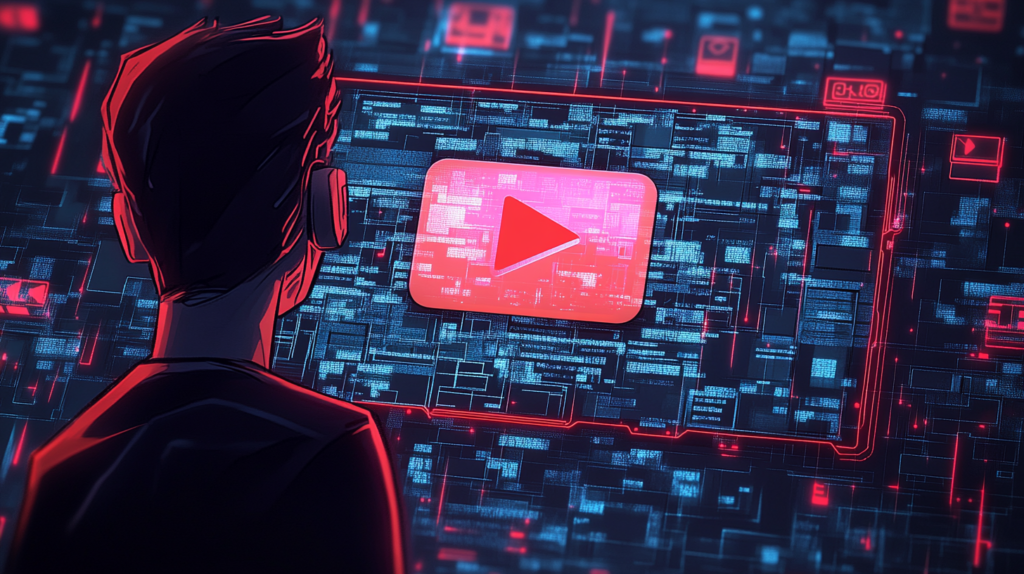
SNSやYouTubeでは、「プログラミングスクールは意味がない」「エンジニアは稼げない」といったネガティブな情報がよく目に入ります。これらの発言には、一定の事実が含まれていることもありますが、発信者側のバイアスや収益構造による「演出」も大きく関係しています。
まず、インパクトのある情報ほどSNSで拡散されやすいという性質があります。「Webエンジニアは最高の職業!」と発信するよりも、「やめとけ」「後悔した」といった刺激的な表現のほうが、多くの人の注意を引き、クリックされやすくなります。つまり、再生数やフォロワー獲得を目的とした戦略的な発言であるケースも少なくありません。
また、過去にスクールに通って失敗した人の経験談が、やや誇張されて共有されることもあります。例えば、学習途中で挫折してしまったり、転職先でうまくいかなかったというケースでは、「スクールは意味がなかった」という結論に結びつきがちです。しかし実際には、「目的とスクール選びがズレていた」「学習時間が足りなかった」といった個別の問題がある場合も多く、すべてのスクールや学習者に当てはまるわけではありません。
さらに、エンジニア業界の本質を知らないまま憶測で話している発信も見られます。たとえば、フリーランスになれば即高収入という幻想を抱いて現実とギャップを感じた人が、業界そのものを否定するような発信をするケースもあります。
このように、SNSや動画での情報は参考になる面もありますが、感情的・演出的なバイアスを見抜くリテラシーも必要です。一次情報だけで判断せず、業界の実情を学び、冷静な目で未来を見据えることが重要です。
プログラミングスクールの選び方が未来を分ける

プログラミングスクール選びは、エンジニアとしての未来を左右するほど重要な分岐点です。「どこでも同じ」と思って適当に選ぶと、学習効率もキャリア展望も大きく違ってきます。とくにWebエンジニアを目指す場合、自分に合ったスタイルとサポート体制があるかを見極めることがカギになります。
まず重視すべきは、カリキュラムの内容です。HTMLやCSSだけで終わるカリキュラムでは、現場で通用する力はつきません。現代のWeb開発では、フロントエンドならReactやTypeScript、バックエンドならNode.jsやデータベース操作、さらにはGitやチーム開発の経験まで必要です。こうした実践的なスキルを段階的に学べるかが非常に重要です。
次に見るべきは、講師の質とサポート体制です。自習中心で質問が通じないようなスクールでは、エラーやつまずきを一人で抱えてしまいがちです。逆に、現役エンジニアがマンツーマンでサポートしてくれるような環境であれば、効率的に理解を深めながら学習を進めることができます。
また、キャリアサポートも見逃せません。単に知識を学ぶだけではなく、ポートフォリオ制作や面接対策、求人紹介まで行ってくれるスクールであれば、転職成功率も大きく変わります。未経験から最短で現場に立つためには、学習と就職支援がセットになっていることが理想的です。
さらに最近では、AIを活用したコーディングサポートがあるスクールも増えてきました。実務では、AIと協働しながら開発効率を上げるスキルも求められるため、そういった環境で学べるスクールを選ぶと、時代に合った学習が可能です。
学ぶ場所によって、学習スピードも理解度も将来の収入も変わります。だからこそ、スクール選びは「なんとなく」で済ませず、自分のゴールとスクールの強みを照らし合わせて、慎重に選ぶべきポイントなのです。
【初心者向け】今から始めるならRANTEQ(ランテック)、侍エンジニア、DMM 生成AI CAMPの違いを知ろう

これからWebエンジニアを目指す初心者にとって、どのプログラミングスクールを選ぶかは非常に重要です。なかでもRANTEQ(ランテック)、侍エンジニア、DMM 生成AI CAMPは、それぞれに明確な特徴があり、目的やスタイルに応じて適切な選択が必要です。
RUNTEQ(ランテック)は、特にWeb開発を本格的に学びたい人に向いています。実践的なチーム開発、Gitを使ったバージョン管理、オリジナルポートフォリオ制作までしっかりカバーしており、まさに「現場に近い学び」が得られるのが強みです。また、全体的にカリキュラムの構成が丁寧で、未経験者でも着実にスキルを積み上げられる設計になっています。
一方、侍エンジニア(SAMURAI ENGINEER)はマンツーマン型でのサポートが充実しており、メンターとの週次面談やSlackでの随時質問など、一人ひとりに寄り添った学習環境が特徴です。特に、自分のペースで進めたい人や、学習のモチベーションを維持したい人に適しています。また、AIを使った学習支援も導入しており、時代に合った効率的な習得が可能です。
そしてDMM 生成AI CAMPは、AI時代に即したエンジニア育成を目的とした先進的なカリキュラムが特徴です。ChatGPTやGitHub Copilotなどの生成AIツールを活用しながら、Web開発やPythonを学び、「AI+エンジニアリング」のスキルを磨くことができます。テクノロジーに強い関心があり、将来的にAIと連携した開発をしたい人には特におすすめです。
このように、どのスクールも強みが異なるため、「何を学びたいか」「どう働きたいか」を明確にしたうえで選ぶことが大切です。自分の理想の働き方を思い描き、それを最短で実現できるスクールを選ぶことが、成功への第一歩となります。
Webエンジニアは今、本当にやめるべきなのか?

- 「Webエンジニアはもう稼げない」
- 「将来性がない」
- 「AIに仕事を奪われる」
そんな声を耳にしたことがあるかもしれません。
確かに、ここ数年で業界の構造や求められるスキルセットは大きく変化しました。しかし、果たして“やめとけ”の声は本当に正しいのでしょうか?
この章では、Webエンジニアを取り巻くリアルな現状を多角的に検証しつつ、「やめるべきかどうか」の判断を冷静に下すための材料をお届けします。
- 増えすぎたエンジニアと競争の現実
- AIの進化による“作業者淘汰”の加速
- スクール卒業後の「理想と現実ギャップ」
- 学習したけど稼げない?その本当の理由
増えすぎたエンジニアと競争の現実

Webエンジニアという職種は、ここ数年で急速に人気を集め、多くの人が転職や副業の手段として目指すようになりました。
その背景には、プログラミングスクールやオンライン学習環境の充実、在宅でも働ける自由度の高さ、そして「未経験から年収1000万」などのキャッチーな文句がある。しかし、そうした情報に背中を押されてエンジニアを目指す人が急増した結果、実際には競争が激化しているのが現実です。
とくにフロントエンド領域(HTML、CSS、JavaScript)においては、数ヶ月の学習で最低限のスキルを身につけることが可能なため、初学者の参入障壁が低い。一方で、企業が求める水準は年々上がっており、ReactやNext.js、TypeScript、あるいはパフォーマンス最適化やセキュリティ知識など、より高度で広範なスキルが要求されるようになっています。
つまり、業界に人が増えたことで、同じスタートラインに立つ人の数が膨れ上がり、「学んだだけ」では通用しない時代に突入したということです。さらに、フリーランス市場でも単価の高い案件には経験者が集まりやすく、未経験者や駆け出しエンジニアは安価な案件の取り合いに巻き込まれがちです。
Webエンジニアという肩書だけでは通用しなくなり、「どんな技術に強いのか」「どんな価値を提供できるのか」がシビアに問われるようになっています。自分のポジションを確立できなければ、増えすぎたエンジニアの波に飲まれて埋もれてしまうのが今のリアルです。
AIの進化による“作業者淘汰”の加速

ChatGPTやCopilotをはじめとする生成AIの台頭によって、エンジニアの仕事のあり方は確実に変わり始めています。かつては人の手で1行ずつ書かれていたコードも、今ではAIがプロンプトひとつでサジェストし、自動生成まで行えるようになりました。
これにより、単純なコーディング作業だけを武器にしていた人、つまり「作業者」に分類されるエンジニアは徐々に淘汰されつつあります。たとえば、HTML/CSSだけのマークアップや、既存テンプレートを元にした簡単なLP制作などは、AIとノーコードツールの併用で済んでしまうケースも少なくありません。
ただし、これはすべてのWebエンジニアが不要になるという話ではありません。逆に、AIを積極的に活用しながら「より高度な設計や提案ができる人」「プロンプトを使いこなして開発の効率を飛躍的に上げられる人」には、これまで以上の価値が認められています。
AIが得意としない、プロジェクトの方向性決定やUX設計、問題解決力が求められる場面では、むしろ人間エンジニアの関与が重要です。
時代は、AIに置き換えられないクリエイティブ思考や文脈理解を持つエンジニアを求めています。ただコードを書けるだけの人材と、AIを使いこなして課題を解決できる人材。今後のWebエンジニアには、この違いがはっきりと評価される時代が来ているのです。
スクール卒業後の「理想と現実ギャップ」

プログラミングスクールでは、短期間でWebアプリケーションを作れるスキルが身についたり、ポートフォリオ制作までサポートがあったりと、一見すると「卒業すればすぐに転職できそう」と思える内容が並びます。しかし、実際にスクールを卒業した人の多くが、その後の“壁”にぶつかっているのが現実です。
たとえば、「ポートフォリオは完成したのに、書類で落とされ続ける」「面接で技術的な深掘りをされて答えられない」「入社後に求められるスピード感についていけない」といった声が聞かれます。
これは、学習内容と実務で求められる内容にギャップがあることが一因です。現場では、バグ修正やコードレビュー、チームでの開発、技術のキャッチアップなど、スクールではなかなか再現しきれない工程が多く存在します。
また、スクール側も「転職成功率○○%」といった実績を掲げてはいますが、その定義が曖昧だったり、実際の就職先がエンジニア職ではないケースも含まれていたりします。そのため、卒業後の未来を過度に期待しすぎると、現実との落差にショックを受けることもあります。
スクールを活用すること自体は間違いではありません。ただし、それをゴールではなく「スタートライン」と認識し、実務経験を積むための工夫や、自走力を育てる努力が不可欠です。スクールで学んだことを“どう使いこなすか”が、その後のキャリアを左右する鍵となります。
学習したけど稼げない?その本当の理由
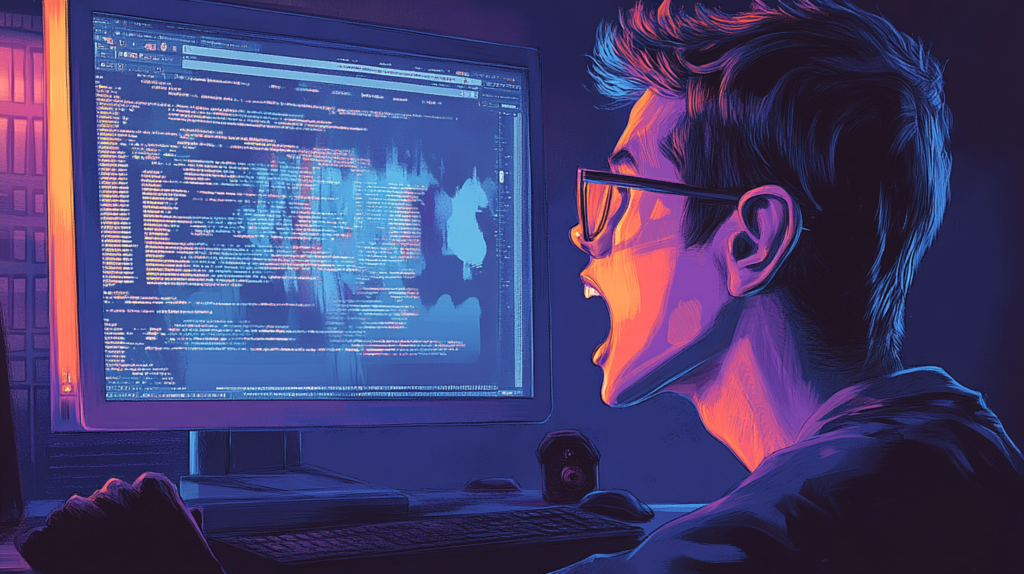
独学やスクールを通じてWeb制作やWebアプリ開発を学んだものの、「なかなか稼げない」「案件が取れない」と感じている人は少なくありません。
その原因は、単にスキル不足というよりも、仕事の獲得方法や市場のニーズとのミスマッチにあることが多いです。
たとえば、ポートフォリオに載せている制作物が、「実務ではあまり使われない技術」であったり、「デザインやユーザー体験が甘い」といった理由で魅力に欠けていることもあります。また、自己流で営業活動をしていると、見せ方や提案内容が相手に響かず、せっかくのスキルが伝わらないまま終わってしまうこともあります。
さらに、単価が低くなりがちなクラウドソーシングにばかり頼っていると、時間に対しての収益が極端に悪く、モチベーションを保つのも難しくなってしまいます。収益化を目指すなら、Web制作だけでなく「マーケティング知識」「課題発見力」「提案力」など、ビジネスに近い視点も身につけていく必要があります。
稼げるWebエンジニアは、単に「コードが書ける人」ではありません。クライアントの目的を理解し、結果に繋がる提案ができる人が信頼を得て、リピートや高単価案件を任されるようになります。学習はあくまで基礎であり、「どう仕事につなげるか」の部分に本気で向き合えるかどうかが分かれ道になります。
Webエンジニアが今“飽和している”って本当?
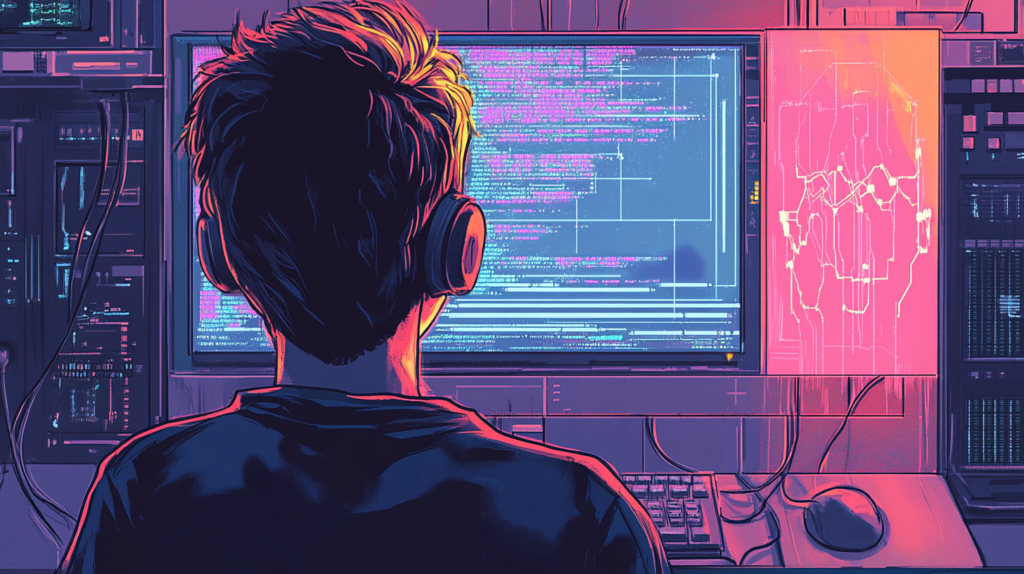
プログラミングスクールの増加や、副業ブームの影響でWebエンジニアを目指す人が急増しています。その一方で、「エンジニアは飽和していて就職できない」「案件の取り合いが起きている」といった声も多く聞かれるようになりました。
果たしてこれは事実なのでしょうか?
この章では、エンジニア数の実情、採用現場の変化、未経験者に求められる条件の変化などをもとに、“Webエンジニア飽和論”の真偽を客観的に掘り下げていきます。
- プログラミングスクール卒が急増中
- 初学者ポジションの倍率が上昇
- 実務未経験の採用難易度は?
- 中堅スキル人材との壁が厚い現実
- 案件の質と数がスクール生の未来を左右する
プログラミングスクール卒が急増中

ここ数年、Webエンジニアを目指してプログラミングスクールに通う人が急増しています。背景には、エンジニア需要の拡大がメディアで盛んに取り上げられたことや、「未経験からでもエンジニア転職可能」といった広告の影響があります。また、副業・フリーランスブームや、テレワーク推進により自由度の高い働き方を求める人が増えたことも大きな要因です。
その結果、スクール卒業生の数は年々増加しており、特に20代後半から30代前半の社会人転職組が目立ちます。各スクールも多様化しており、短期集中型からオンライン完結型、AIやデータ分析に強みを持つコースまでさまざまです。RUNTEQのような現場志向のスクールや、侍エンジニア(SAMURAI ENGINEER)、DMM 生成AI CAMPといったAI活用を前提としたカリキュラムが支持を集めているのも、この流れの一部といえます。
一方で、スクール卒業後にすぐにエンジニアとして活躍できるとは限らないという現実も見逃せません。卒業直後のスキルやポートフォリオの質、面接時のコミュニケーション力などによって、転職成功率には大きな差が出ています。スクールに通えば安心、という時代ではなくなりつつあるのです。
初学者ポジションの倍率が上昇

プログラミングスクール卒業生が増えることで、企業が募集する初学者・未経験者向けのポジションの倍率は確実に上がっています。特に人気のある「研修付き正社員求人」や「完全未経験OK」「チーム開発あり」といった条件の良い求人は、数十人、場合によっては百人以上の応募が殺到するケースもあります。
このような高倍率の状況では、採用担当者が重視するポイントも変わってきています。単なるHTMLやCSSの知識ではなく、実務レベルのJavaScript、React、API連携などのフロントエンドスキルや、LaravelやRuby on Railsなどのバックエンドスキルまで問われることも増えています。また、Gitやチーム開発の経験、基本的なエラー処理の考え方などもアピール材料になります。
特に実務経験がない場合、完成度の高いポートフォリオやGitHubでのアウトプット、そして「なぜこの技術を選んだのか」「どんな課題があってどう解決したのか」といった説明力が大きな武器になります。スクールで教わった内容を自分なりに咀嚼し、他の受講生との差別化を図る工夫が必要不可欠です。
実務未経験の採用難易度は?

実務未経験からWebエンジニアとして採用される難易度は、以前と比べて確実に上がっています。特に2023年以降は、エンジニア志望者の供給が増えすぎたことで、企業側が未経験者の採用に慎重になっている傾向が顕著です。
現場では「即戦力化までに時間がかかる」「教育コストが高い」といった理由で、未経験者の採用枠を絞る企業も出てきています。たとえ未経験歓迎の求人であっても、何らかの実績や学習姿勢を示さなければ、書類選考で落とされてしまうことが多くなっています。
一方で、AIを活用した問題解決や効率的な開発ができるスキルを持つことで、評価が高まるケースも出てきています。たとえば、ChatGPTを使ってコードの構文エラーを修正した経験や、AIを活用したUI改善の提案をポートフォリオに組み込んでいる受講生は、企業からの関心も高まる傾向にあります。
未経験だからこそ、どのようにして知識を身につけ、技術的課題に立ち向かったのかを具体的に伝えることが採用への鍵となります。形式的な自己PRではなく、自分の学習プロセスをストーリーとして語れるかが重要なのです。
中堅スキル人材との壁が厚い現実

未経験エンジニアが最初に直面する現実のひとつが、すでに現場で活躍している中堅層との圧倒的なスキル差です。中堅エンジニアは、フレームワークを深く理解し、設計から実装、テスト、デプロイまで一貫して行うスキルを持っており、トラブル発生時の対応力にも優れています。
このような中堅人材は企業から高く評価されるため、同じ土俵で比較された場合、未経験者は不利になりがちです。特にベンチャー企業やスタートアップなど、即戦力を求める傾向が強い現場ではこの傾向がより顕著です。
さらに、最近ではミドル層もAIツールを積極的に導入しており、開発効率の高さがより重視されるようになっています。たとえば、GitHub CopilotやChatGPTを組み合わせて高速に開発できることは、技術力と生産性の両面で評価されます。
未経験者がこの壁を超えるためには、スクールでの学習に加え、個人開発やチーム開発、OSSへの貢献など、スキルを実践で試す場を増やすことが有効です。数ヶ月の経験の差であっても、現場でのアウトプットによってその差を少しずつ埋めていくことが可能です。
案件の質と数がスクール生の未来を左右する
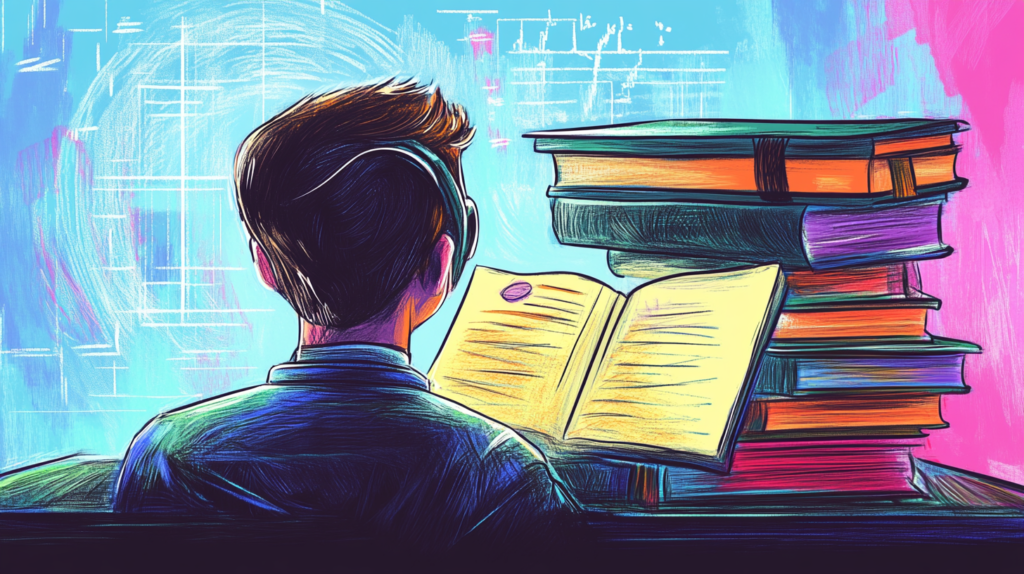
Webエンジニアとしてのキャリアをスタートするうえで、どのような案件に関われるかは非常に重要です。たとえば、初期に関わった案件が単純なHTML修正や運用保守に限られてしまうと、スキルの幅がなかなか広がりません。逆に、開発の要件定義や設計から関われる案件であれば、経験値の伸びが大きく、次のステップへの道が開けます。
現在の市場では、案件の数自体はまだ一定数存在しますが、スクール生の急増により一人あたりが関われる良質な案件の取り合いが激しくなっています。クラウドソーシングなどを活用しても、単価が低く、評価につながりにくいタスクも多いため、いかに良質な案件にたどり着けるかが分岐点となります。
特にスクール卒業後の数ヶ月で、どのような実務に触れられるかは、その後の成長速度に大きな影響を与えます。この意味でも、スクール選びは慎重に行うべきです。現場に近い課題に取り組めるRUNTEQや、AIを駆使したアプローチが学べるDMM 生成AI CAMPなどは、卒業後のスタートラインを引き上げてくれる選択肢といえるでしょう。
スキルアップの道を切り拓くためには、案件の「数」だけでなく「質」にも着目し、自分の学びたい分野やキャリア像に合った経験を積むことが求められます。
Webエンジニアの仕事は激務?働き方のリアルとは

Webエンジニアは「激務」「残業地獄」「ブラック」といったイメージを持たれがちですが、実際の働き方はどうなのでしょうか?
業界や会社の種類によって、働き方や労働環境は大きく異なります。
本章では、スタートアップ・受託開発・自社サービス企業など、働く場所による違いや、リモートワークやフレックス制度の現状、さらには「激務になりにくいキャリア設計」のヒントまで、Webエンジニアのリアルな労働事情を徹底解説します。
- 長時間労働と納期ストレスの正体
- スタートアップ・受託・自社開発で違う?
- リモートワークと裁量労働の光と闇
- “激務にならない働き方”を選ぶには
- 福利厚生・労働環境の改善トレンド
長時間労働と納期ストレスの正体
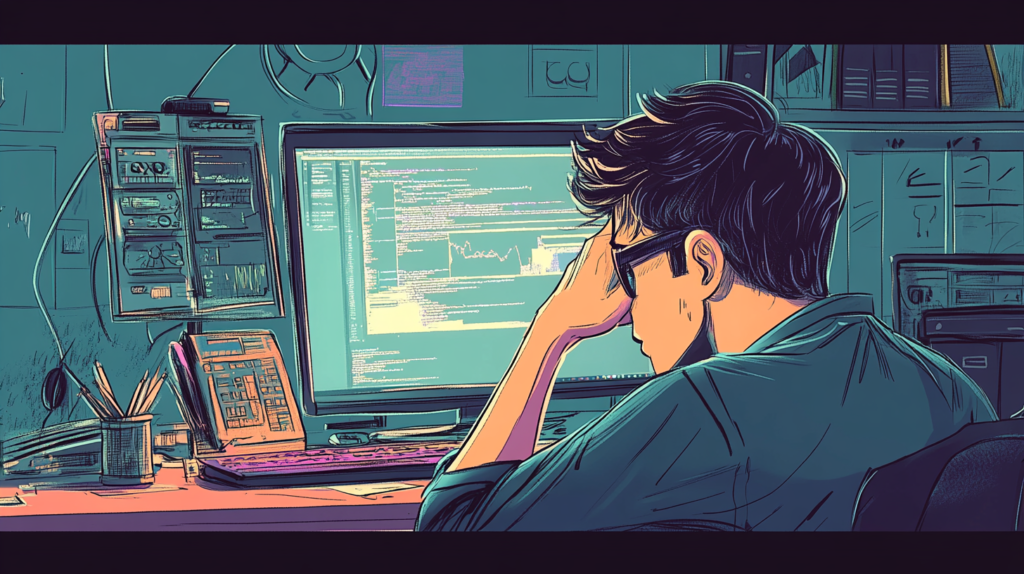
Webエンジニアの仕事において、長時間労働と納期ストレスは避けて通れないと感じている人も少なくありません。その原因のひとつは、プロジェクトの進行におけるスケジュール管理の甘さや、クライアントとの調整不足です。とくに受託開発の現場では、納期を優先するあまり現場のリソースを無視した無理なスケジュールが組まれ、結果的に残業や休日出勤につながることがあります。
また、開発工程で発生するバグ修正や仕様変更が直前になって発生することも少なくなく、これがさらなる工数の増加を招きます。納期が近づくと「リリースしなければならない」というプレッシャーが増し、精神的なストレスも蓄積されていきます。
さらに、エンジニア自身が完璧主義である場合、「品質を落としたくない」という意識から、自主的に作業時間を延ばしてしまうこともあります。これは周囲からの評価にもつながる一方で、自分自身の健康を犠牲にしてしまうリスクがあります。
こうした長時間労働を避けるには、チームやマネージャーとタスク管理をこまめに共有すること、開発初期からリスクヘッジの時間を見積もっておくことなど、組織と個人の双方の工夫が必要になります。
スタートアップ・受託・自社開発で違う?

Webエンジニアの働き方や求められるスキル、そして仕事量は、どのタイプの企業に所属するかによって大きく異なります。スタートアップ、受託開発、自社サービスを手がける企業では、環境や価値観にも明確な違いがあります。
まずスタートアップ企業では、「スピード感」や「一人が担う役割の広さ」が特徴です。まだ体制が整っていない中でプロダクトを早急に市場に出す必要があり、エンジニアは設計から実装、運用まで幅広く担当します。そのぶん成長スピードは早いですが、タスクが集中しやすく、業務時間が長引く傾向もあります。
受託開発の現場では、クライアントからの要望に応える形でプロジェクトが進行します。プロジェクトごとに仕様や使用技術が異なるため、多様な技術に触れられる一方、納期と予算に追われることが多く、やりがいや裁量の面で物足りなさを感じることもあります。
一方で自社サービスを運営している企業では、自分たちのペースでサービス改善を行えるため、納期プレッシャーは比較的少なめです。サービスの成長と共に中長期で技術力を高められる点も魅力ですが、その分安定したスキルと責任感が求められます。
このように、同じWebエンジニアでも環境によって働き方のストレスややりがいが大きく変わるため、自分に合ったフェーズや企業文化を選ぶことが非常に重要です。
リモートワークと裁量労働の光と闇

Webエンジニアの仕事は、他の職種に比べてリモートワークや裁量労働制と相性が良いとされています。実際、多くのIT企業ではコロナ禍を機にリモート体制を導入し、時間と場所に縛られない働き方が広まりました。
リモートワークの光の部分は、自宅や好きな場所で働けることで通勤のストレスがなくなり、ライフスタイルに合わせた柔軟な働き方が可能になる点です。集中できる環境を自ら整えることで、生産性が向上したという声も多く聞かれます。
しかしその一方で、「闇」とされる部分も存在します。例えば、コミュニケーションの断絶です。チームとの意思疎通がうまくいかず、ちょっとした認識のズレが大きなミスに繋がることもあります。また、自宅での作業が長引くことでオンとオフの境目が曖昧になり、気づかないうちに長時間労働になっているケースも少なくありません。
裁量労働制に関しても、成果さえ出せば勤務時間に縛られないという自由さはあるものの、その分成果主義が強まり、プレッシャーも大きくなります。とくに若手エンジニアは「何をもって成果とするか」が曖昧なまま放置され、逆に働きづらさを感じてしまうことがあります。
これらの働き方を自分に合った形で活用するためには、セルフマネジメント能力やタイムマネジメントの意識が不可欠です。

“激務にならない働き方”を選ぶには

激務を避け、持続可能なキャリアを築くためには、働く企業や職場環境の選び方に注意する必要があります。とくにWebエンジニアのように専門性が求められる職種では、自分のスキルと志向に合致した環境を選ぶことで、長時間労働や過度なストレスを回避しやすくなります。
まず重要なのは、会社選びの段階で「開発体制」や「プロジェクト管理方法」などを確認することです。たとえば、アジャイル開発を導入している企業は、定期的なスプリントレビューや振り返りを行うことで、無理なスケジュールを避ける傾向があります。
また、エンジニアの評価基準やチームのコミュニケーション文化も大きなポイントです。属人化しているプロジェクトや、マネージャーとの距離が遠い環境では、トラブルが起きたときにサポートが得られず、結果的に個人に業務が集中してしまいます。
さらに、労働条件だけでなく、成長環境の有無も注目すべきです。社内勉強会が活発な企業や、技術カンファレンス参加を支援してくれる制度がある会社では、スキルアップと業務効率の両方が実現しやすくなります。
転職時や就職活動時には、企業の口コミやエンジニアのブログなどを調べ、できるだけ現場の声を参考にするのがおすすめです。可能であれば、面接時に具体的な一日の流れや残業時間について質問してみると、働き方の実情が見えてきます。
福利厚生・労働環境の改善トレンド

近年、Webエンジニアを取り巻く労働環境には改善の兆しが見られています。エンジニア人材の獲得競争が激しくなる中で、企業側も「働きやすさ」や「福利厚生の充実」に力を入れるようになってきました。
例えば、リモート勤務を前提としたフルリモート体制の導入や、フレックスタイム制度によって通勤やライフスタイルの自由度を高める取り組みが広がっています。また、開発者向けにPCやディスプレイ、椅子などの備品支給制度を設ける企業も増えており、自宅でも快適に作業ができるよう配慮されています。
福利厚生の面では、学習支援制度や副業解禁の流れも強まっています。資格取得補助や書籍購入費の支援、技術カンファレンスの参加費補助などを通じて、個人のスキルアップを後押しする文化が根付きつつあります。
メンタルケアや健康支援にも力を入れる企業が増えており、産業医による相談体制や、ストレスチェックを定期的に行う体制を整えている会社もあります。
こうした改善の背景には、エンジニアの離職率の高さへの危機感があります。優秀な人材を長期的に確保するために、働き方の柔軟性やサポート体制の整備は、今後ますます重要な経営戦略の一つとなっていくでしょう。
AI時代のWebエンジニア像とは?“普通”が変わっていく

ChatGPTやGitHub CopilotのようなAIツールが日常に溶け込み、もはや「AIを使えること」はWebエンジニアの“基本スキル”となりつつあります。従来のように手打ちでコードを書けるだけでは評価されにくくなり、「AIをどう活用してより早く・より質の高いアウトプットを出せるか」が問われる時代。
ここでは、これから求められるWebエンジニア像の変化や、AIを活用する人・される人の分かれ道、そして「AIを味方にできるエンジニアになるためのヒント」を解説していきます。
ChatGPTやGitHub Copilotの実用レベル
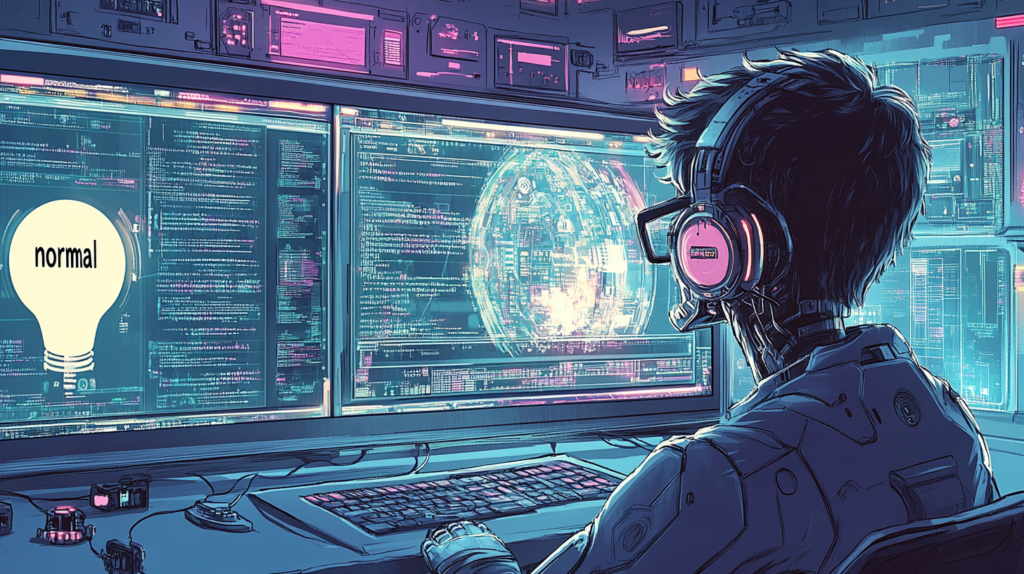
現在、ChatGPTやGitHub CopilotといったAIツールは、Webエンジニアの日常業務において実用的なレベルまで進化しています。単なるコードの補完にとどまらず、業務に直結する形で幅広い作業を支援できるようになっています。
たとえば、GitHub Copilotを使えば、関数の定義やAPIの呼び出し、Reactコンポーネントの実装までを、自然言語での指示から自動生成できます。タイピングの手間を大きく減らすだけでなく、公式ドキュメントを調べる時間の短縮にもなり、生産性が格段に向上します。
また、ChatGPTでは複雑なアルゴリズムの実装や、バグの原因特定、コードのリファクタリング案の提示まで行えるため、特にひとりで開発を進めるフリーランスや学習中の人にとっては心強いサポーターになります。
加えて、技術的な知識を事前に完全に持っていなくても、AIの提案をヒントに試行錯誤することで、実装力を磨くことも可能です。たとえば、Node.jsの環境構築や、Vue.jsでのコンポーネント間通信など、手間のかかるステップもチャット形式で相談しながら進められるため、学習コストのハードルが一気に下がりました。
とはいえ、完全に任せきりにできるというわけではありません。AIは与えられた文脈や指示に基づいてコードを生成するため、要件があいまいだったり、設計が不十分だったりすると的外れなアウトプットが返ってくることもあります。つまり、AIを「使いこなす」スキルも重要です。
現時点でも、こうしたAIツールは十分に実用的であり、使える人ほど生産性が上がる時代に入っています。Webエンジニアにとっては、AIを使わない理由が見当たらないと言っても過言ではありません。
AIでできること・できないこと

AIツールが急速に進化している一方で、何でもかんでも任せられるわけではありません。Webエンジニアの仕事を代替する部分と、まだ人間でなければ難しい部分を正しく理解することが、これからのキャリア形成において重要なポイントとなります。
まず、AIが得意としているのは「パターン化された処理」や「既存知識に基づいた回答」です。たとえば、よく使われるコードスニペットの生成や、既存の機能に対する簡単な修正、マークアップ作業、APIとの連携など、ある程度定型化された業務はAIに任せることができます。特に、フロントエンドにおけるボタンの実装や、ログイン機能のような再利用性の高いパーツは、AIの得意分野です。
一方で、完全に任せるのが難しいのは「プロダクトの要件定義」「ビジネスロジックの設計」「新しいUI/UXの提案」など、抽象度が高く、文脈に強く依存する作業です。たとえば、ユーザー体験を重視した設計や、競合との差別化を図る独自仕様の開発、プロジェクトの目的を踏まえた技術選定などは、人間の判断や感性が必要とされる領域です。
また、AIにはリアルタイムでの実行環境や動作確認を行う能力がないため、生成されたコードの動作確認やテストの実施、パフォーマンスチューニングといった工程は人間の手が欠かせません。さらに、倫理的な判断やセキュリティに関する慎重な対応も、現在のAIでは不十分なことが多いです。
要するに、AIは「道具」としては非常に有能ですが、それをどう活用するかはエンジニアの力量にかかっています。できることとできないことを見極め、AIを最大限活用できるポジションに立てる人が、今後ますます重宝されるでしょう。
AIに使われる人 vs AIを使う人の差
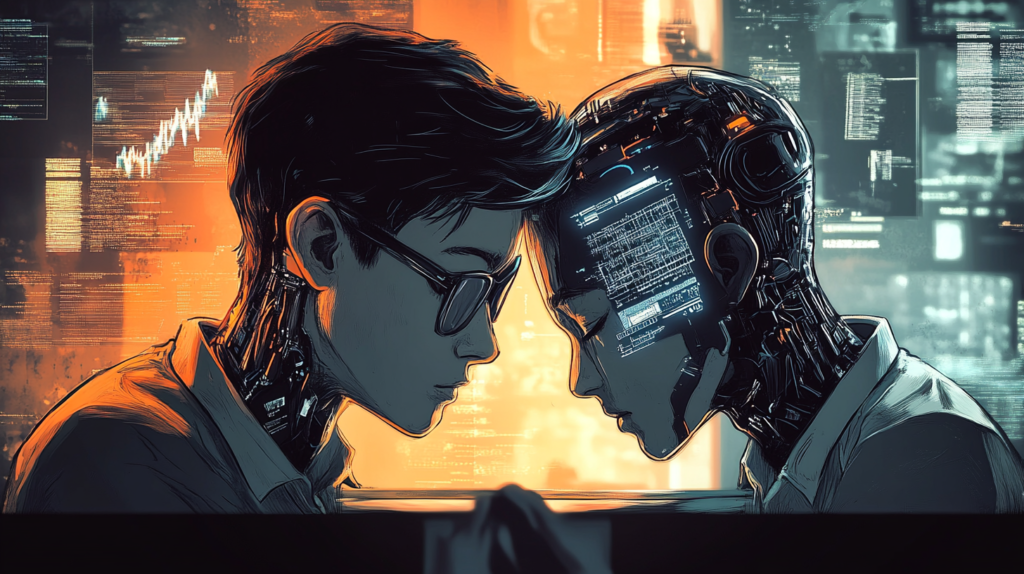
AI時代の到来により、Webエンジニアにはこれまで以上に大きな「差」が生まれるようになっています。それは、AIに“使われる人”と、AIを“使いこなす人”の違いです。この差は、単なるツールの習熟度ではなく、思考のスタンスや働き方そのものに直結しています。
AIに使われる人とは、たとえば提示されたコードをそのままコピペして使い続けるだけで、自分で設計や改善を行わないようなスタイルのエンジニアを指します。こうした人は短期的には便利さを享受できますが、次第に「誰でもできる作業」に埋もれてしまい、付加価値の低い存在になってしまうリスクがあります。特に、作業の意味や背景を理解せずに機械的に指示されたことだけを実行するような働き方では、AIによって容易に代替されてしまいます。
対して、AIを使いこなす人は、AIからの提案を“起点”として自分の思考を展開できる人です。たとえば、AIの生成したコードに対して「なぜこの構造なのか」「もっと効率の良い書き方はないか」と疑問を持ち、自分なりにアレンジや最適化を加えることができる人です。また、AIをプロジェクトの一員のように扱い、スピーディにアイデアを形にするためのツールとして使っている点も特徴的です。
この違いは、将来的な年収やキャリアの選択肢にも大きく影響します。AIをうまく使えるエンジニアは少人数のチームでも多くの成果を出せるため、企業からの需要も高く、フリーランスとしても高単価案件に参画しやすくなります。
つまり、同じツールを使っていても、扱い方ひとつでキャリアが大きく変わる時代に突入しているということです。だからこそ、AIに任せて安心するのではなく、AIを通して自分の力を拡張する姿勢が、これからのWebエンジニアに求められていくのです。
コーディング補助・問題解決はAI前提になる
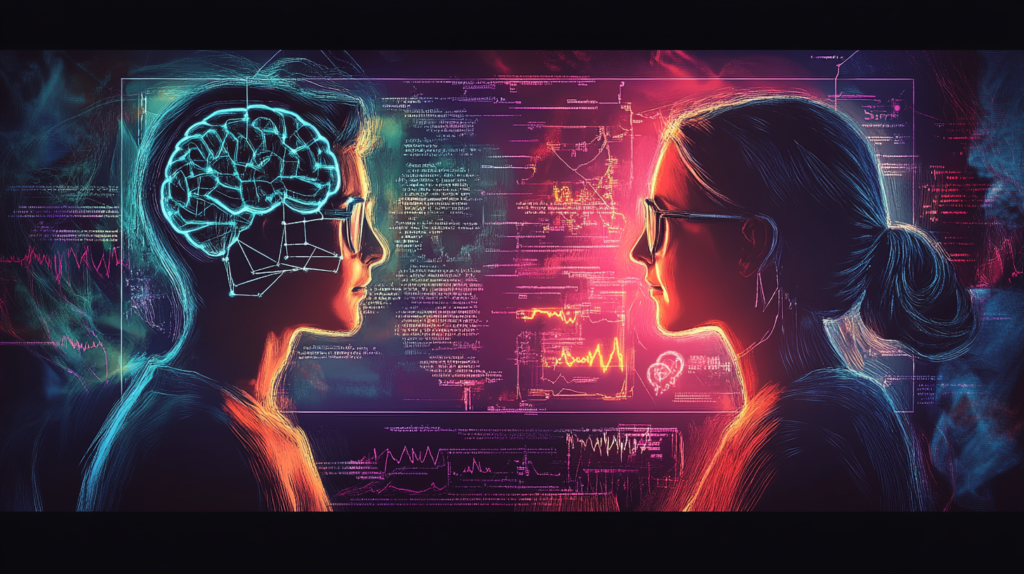
今や多くの現場で、コーディング作業やバグの解決にAIが活用されるのは当たり前になっています。
ChatGPTやGitHub Copilotをはじめとする生成AIは、コードの自動生成だけでなく、設計の提案やエラーの原因特定、ライブラリの選定にまで利用されています。これまで「ググって調べる」「公式ドキュメントを読み解く」といった工程に時間をかけていたエンジニアも、AIに自然言語で質問することで数分のうちに答えが得られるようになりました。
これにより、求められるWebエンジニアのスキルも変わってきています。以前は「コードを一から書けること」が重視されていましたが、現在では「AIに適切な指示を与えて目的のコードを出力させられるか」「AIの出力を正しく理解し、修正できるか」が大切になっています。つまり、AIを“使う側”に回れるかどうかが、そのままエンジニアとしての市場価値に直結します。
現場でも、「AIで効率的に作業が進められる人材」と「AIをうまく活用できず生産性が伸び悩む人材」とでは、成果にも大きな差が出始めています。新しい技術に柔軟に対応できるエンジニアは、今後もAIと共に進化していくことが期待されます。
学習もAIで高速化!DMM生成AI CAMPの実例

AI時代のWebエンジニア育成に特化した学習環境として注目されているのが「DMM 生成AI CAMP」です。従来のプログラミングスクールでは講師に質問したり、自分で時間をかけて調べながら学習を進めるスタイルが一般的でしたが、DMM生成AI CAMPではその常識が大きく変わります。
このスクールでは、ChatGPTをはじめとする生成AIを日常的に学習に取り入れており、受講生はわからないことをすぐにAIに聞いて、その場で実装例を見たり、エラー解決に活用することができます。たとえば、JavaScriptの特定の挙動について調べる際も、AIに簡単な質問をするだけで、わかりやすいサンプルコードと共に解説を提示してくれます。
また、AIを使って学習効率を高めるだけでなく、どのように質問すれば良質な回答が得られるのか、AIとのやり取りのテクニックについても体系的に学ぶことができます。これは、今後の実務でも大いに役立つスキルです。
DMM生成AI CAMPの受講者の中には、未経験からスタートしてもAIを駆使することで、数ヶ月で実務レベルの開発に対応できるようになった例もあります。短期間で結果を出したい人にとって、AIを前提とした学習環境は非常に心強い味方になるでしょう。
サムライエンジニアなら「AI×人間力」も強化可能

Webエンジニアとして生き残るためには、AIを使いこなすスキルだけでなく、チームでの協調性や顧客とのやり取りといった「人間力」も重要です。その両方をバランスよく身につけられるのが、サムライエンジニアです。
侍エンジニア(SAMURAI ENGINEER)では、マンツーマン指導を軸としながら、ChatGPTなどのAIツールの活用方法についても実践的に学べるカリキュラムが組まれています。コードをただ書くだけではなく、「この要件をどう満たすか?」「ユーザーにとって何が使いやすいか?」といった、ビジネス視点を持った設計や提案力も育てることができます。
特に評価されているのは、AIが出した答えに対して「本当にこれでいいのか?」「他にもっと良い解決方法はないか?」と考える訓練ができる点です。これにより、AIの提案にただ従うだけでなく、自らの判断で質の高いアウトプットを出せるエンジニアを目指すことができます。
また、面接対策やポートフォリオ作成のサポートも充実しており、AI時代に求められる「技術力+人間力」を両輪で鍛えたい人にとって、非常に実践的なスクールとなっています。将来、チームリーダーやフリーランスとして活躍したい人にもおすすめの学習環境です。
【迷ってる人向け】今から目指すなら「Webエンジニア+〇〇」の時代へ

- 「Webエンジニアを目指すのはもう遅いのでは?」
- 「AIに仕事を奪われるんじゃ…」
そんな不安を抱えていませんか?
たしかに、かつての“HTMLとCSSが少し書ければOK”な時代は終わりを迎えました。でも安心してください。
今は“Webエンジニア+〇〇”という複合スキルが武器になる時代。
マーケティング、デザイン、AI、ビジネス視点――どれか一つを掛け合わせることで、あなたの価値は一気に跳ね上がります。
本章では、未経験からでも目指せる“強いエンジニア像”と、具体的なスキル戦略をわかりやすく解説します。
- 技術×マーケで強いWeb人材になる
- デザイン思考やSEO知識も武器になる
- プロダクト志向でSaaSに関われる人材に
- キャリアは一本道じゃない。柔軟な構築が重要
技術×マーケで強いWeb人材になる

近年のWebエンジニアには、単にコードを書くだけでなく、その技術がどのようにビジネス成果に結びつくかを理解できることが求められています。とくにWeb領域においては、マーケティングとエンジニアリングの融合が大きな武器になります。
たとえば、ユーザーの行動データをもとにサイト改善を行うA/Bテストでは、マーケターの分析力とエンジニアの実装力が両立して初めて意味のある結果が得られます。WebサイトやプロダクトのCVR(コンバージョン率)を向上させる施策では、マーケ側が「どうすれば人が行動するか」を設計し、エンジニアが「それをどのように技術で実現するか」を考えることが重要です。
最近では、GA4やヒートマップ、Looker Studioといった分析ツールのデータを見ながらフロントエンドを調整できるエンジニアは特に重宝されています。また、マーケティングオートメーションやCRMとの連携など、Webの裏側にある業務プロセスに技術で介入できる人材は、企業にとって事業成長に直結する存在になります。マーケティング思考を取り入れることで、「ただの作業者」から「成果を出せるWeb人材」へと進化できるのです。
デザイン思考やSEO知識も武器になる

Web開発の現場では、技術力だけでなく「どのようにユーザー体験を作るか」という視点が欠かせません。その中でも、デザイン思考とSEOの知識は、Webエンジニアにとって重要な補助スキルになります。
デザイン思考とは、ユーザー視点に立って課題を発見し、創造的な方法で解決策を考えるプロセスです。UI/UXの改善に取り組むときには、単に見た目の良さではなく、ユーザーが目的をスムーズに達成できる導線設計が求められます。HTML/CSS/JavaScriptを使って「気持ちいい体験」を作れるエンジニアは、プロダクトチームでも重宝されます。
一方で、SEO(検索エンジン最適化)についても、現代のWeb開発では無視できません。どれだけ技術的に優れたサイトでも、検索結果に表示されなければユーザーはたどり着けません。構造化データの実装、ページの読み込み速度の最適化、メタ情報の適切な管理などは、フロントエンドエンジニアが実装できるSEO施策の一例です。技術×ユーザー視点×集客という三軸を理解しながら設計できるWebエンジニアは、市場価値が非常に高い存在になります。
プロダクト志向でSaaSに関われる人材に

現代のスタートアップや成長企業の多くは、SaaS(Software as a Service)を中心としたプロダクト開発を行っています。こうした現場では、「機能を作って終わり」ではなく、サービスとして継続的に改善し続ける姿勢が求められます。そのため、プロダクト志向を持ったWebエンジニアは特に価値が高く、チームの中心的な存在になれることが多いです。
プロダクト志向とは、「この機能はユーザーにとって本当に必要なのか」「継続的に価値を提供するにはどう改善すべきか」といった視点を常に持ち、開発に取り組む姿勢のことです。たとえば、ユーザーの離脱率が高い導線をデータから分析し、技術的な修正だけでなく、機能の見直しやUI改善を自発的に提案できる人材は、SaaS開発チームにとって非常にありがたい存在です。
また、SaaSでは長期的に機能を保守・改善し続けるため、設計段階での拡張性やテストのしやすさも重要になります。コードの品質や保守性にも気を配れるエンジニアは、プロダクト全体の成長に寄与するキーパーソンになり得ます。単に「作る」から一歩進んで「育てる」Webエンジニアを目指すことが、これからのキャリアには必要です。
キャリアは一本道じゃない。柔軟な構築が重要

かつては「エンジニアになったら、ずっとコードを書いてキャリアを積む」といった一本道の考え方が主流でしたが、現代ではまったく異なる景色が広がっています。Webエンジニアとしてのキャリアは、技術力の深化だけではなく、デザインやマーケティング、マネジメント、事業開発といった他分野と組み合わせることで多様に枝分かれしていきます。
たとえば、フロントエンドから始めた人がUXに強くなり、のちにプロダクトマネージャーとして活躍することもありますし、バックエンドからデータ分析やAI開発にキャリアチェンジする例も増えています。副業やフリーランスという選択肢も含めれば、「どこで働くか」「どんな働き方をするか」もかなり自由度の高い時代です。
また、ライフイベントや価値観の変化に合わせて、キャリアの再構築ができる柔軟性は非常に重要です。育児や介護などの事情があっても、リモートワークやスキルのポートフォリオ化により、場所や時間に縛られずに働くことが可能です。今後さらに進化するAIツールを活用すれば、個人の生産性は飛躍的に向上し、自分らしいキャリアを選びやすくなるでしょう。
一本道ではなく、自分で設計して、必要に応じて軌道修正できる「しなやかなキャリア構築」こそが、これからのWebエンジニアにとってのリアルです。
【結論】Webエンジニアはやめとけ? → それは“時代遅れの視点”です
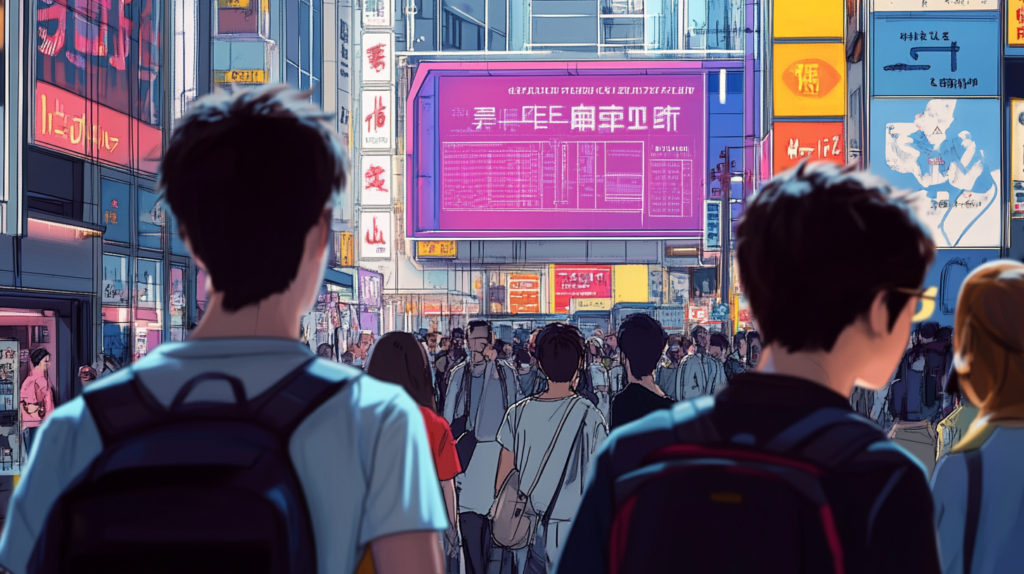
Webエンジニアに関して「オワコン」「稼げない」「やめとけ」といった言葉が飛び交う今の時代。しかし、それらは一面的で時代遅れな視点にすぎません。確かに、AIの進化や競争の激化により、“ただの作業者”は淘汰されつつあります。
ですが、AIを活用しながら価値を生み出せるWebエンジニアは、むしろこれからの時代において重要なポジションを担っていきます。この記事の最後では、なぜ“やめとけ”が通用しないのか、そしてどうすれば“求められるエンジニア”としてキャリアを築けるのかを、まとめてお伝えします。
迷っているあなたにこそ読んでほしい、結論パートです。
- 作業者は淘汰される、でも創造者は求められる
- AI活用スキルを持つ人が“普通”になる未来
- 迷う人はスクールで「答え合わせ」してみよう
- Ranteq・サムライ・DMMなど、自分に合う環境を選べ
作業者は淘汰される、でも創造者は求められる

近年、Web開発の現場では「ただ言われた通りに作る」だけのエンジニアは、確実に価値を失いつつあります。これはAIの進化や、ノーコード・ローコードツールの普及によって、単純な作業を自動化できるようになったことが大きな要因です。特に、静的なHTMLやCSSをコーディングするだけの仕事は、もはやAIにとっては朝飯前です。
ですが一方で、「こんな機能を加えればもっと便利になる」「ユーザーの導線を改善しよう」といった、提案力やクリエイティブな発想ができるWebエンジニアの価値はむしろ高まっています。単なる実装担当者ではなく、プロダクトの成功を見据えて考え、開発をリードできる人材は、今後も重宝されるでしょう。
さらに、バックエンドとフロントエンドを横断的に理解し、AIツールやAPIを使いこなして複雑な問題を解決できるスキルを持つエンジニアは、プロジェクト全体の中で存在感を発揮します。だからこそ今は「作業者としてのWebエンジニア」ではなく、「価値を創造する立場で関わるWebエンジニア」を目指すことが求められています。
AI活用スキルを持つ人が“普通”になる未来

少し前までは、「AIを使ってコードを書くなんて未来の話」と感じていた人も多いかもしれません。ですが現在では、ChatGPTやGitHub CopilotのようなAIツールを日常的に使って開発を進めるエンジニアが急増しています。特に、トラブルシューティングやコードの雛形生成、パフォーマンス改善の提案などは、AIを活用することで圧倒的にスピードアップすることが可能になっています。
つまり、これからのWebエンジニアにとって「AIを使う能力」は特別なものではなくなっていくでしょう。むしろ、AIを活用できないことが“遅れたエンジニア”として見られるリスクになりつつあります。
AIに任せられるところは任せ、自分は論理設計やUI/UX改善などに集中する。そんな“ハイブリッド型”のスキルセットを持つエンジニアが、これからの主流になっていきます。AIを上手に使いこなすことで、アウトプットの質もスピードも上がり、結果的に報酬や評価にも直結するようになるのです。
迷う人はスクールで「答え合わせ」してみよう
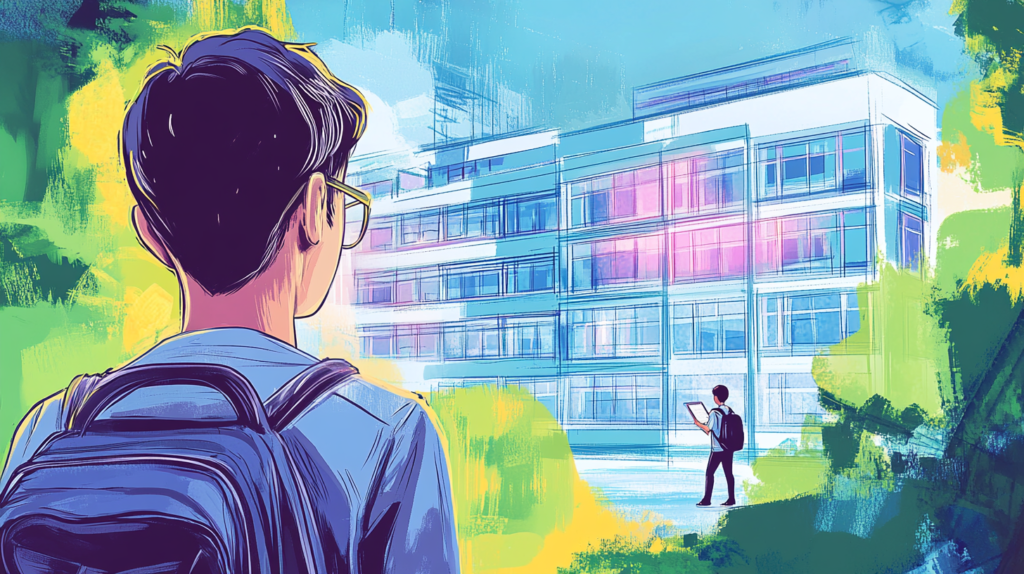
「Webエンジニアって将来性あるの?」「自分に向いてるかわからない」と感じている人にとって、最も効率の良い答えの出し方は、実際に学習を始めてみることです。なかでも、スクールに通うことで体系的に学びながら、現場視点の知識にも触れることができます。
独学では得られにくい現場のリアルや、学ぶ順番、エラーの乗り越え方を知るだけでも、向き・不向きの判断はしやすくなります。また、スクールの多くは無料体験やカウンセリングを実施しており、学び始める前に疑問点をクリアにすることも可能です。
Webエンジニアというキャリアに少しでも興味があるなら、まずは数週間だけでも「擬似体験」してみると、自分の中で納得感を持った判断ができるようになります。迷ったまま時間だけが過ぎるより、トライしてみた結果から判断した方が、後悔は少ないはずです。
Ranteq・サムライ・DMMなど、自分に合う環境を選べ

Webエンジニアとしてのスキルを本格的に伸ばしたいなら、自分に合った学習環境を選ぶことが大切です。たとえば、Web開発に特化して即戦力になりたい場合は「RUNTEQ」のように実践重視のカリキュラムが組まれているスクールが適しています。実務経験に近い開発演習が多く、ポートフォリオ作成にも力を入れている点が評価されています。
一方で、AIを活用したWeb開発や、最新の技術トレンドに強くなりたい人には、「侍エンジニア(SAMURAI ENGINEER)」や「DMM 生成AI CAMP」も注目されています。
これらのスクールでは、AIツールの使い方や効率的な問題解決法など、時代にマッチしたカリキュラムが提供されており、今後のWebエンジニアに必要なスキルを習得できます。
また、サポート体制や学習スタイル(対面/オンライン、マンツーマン指導など)もスクールごとに異なるため、事前に比較・相談してから選ぶのが理想です。無料相談会を活用して、実際のカリキュラム内容や雰囲気を掴んでから決めると安心です。
自分にとって「続けやすい」「伸びやすい」環境を選ぶことで、学習効率もモチベーションも大きく変わります。今は、スキルを武器にして未来を切り拓ける時代です。スクール選びは、その第一歩とも言えるでしょう。